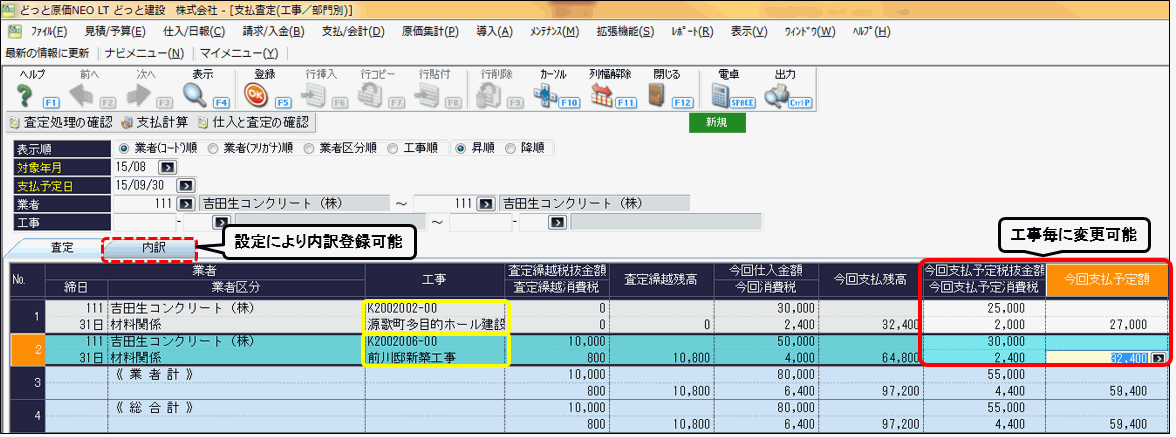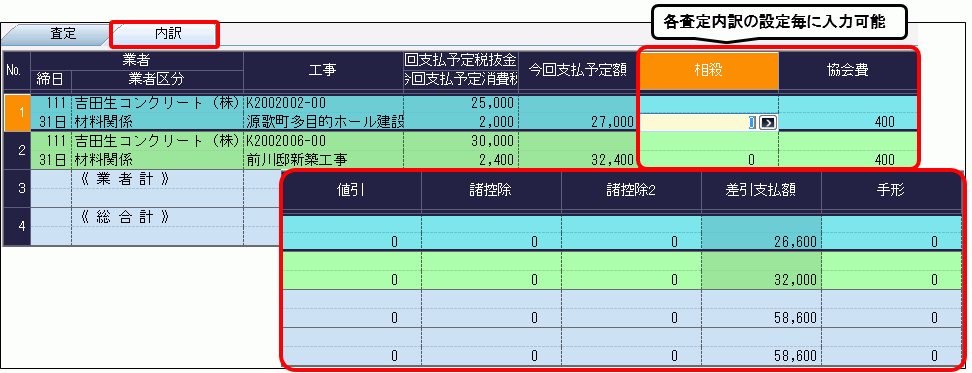支払査定方法について
支払の査定方法は、以下5種類あります。
①仕入額を支払する、②業者単位に査定する、③工事単位に査定する、④注文番号単位に査定する、⑤伝票単位に査定する
それぞれの具体的な査定方法は以下の通りです。
【Ⅰ 各査定方法による支払査定内訳設定の有無】
|
支払査定内訳 |
||||
|
手形 |
協力会費 |
相殺 |
その他控除 |
|
|
①仕入額を支払する |
- |
- |
- |
- |
|
②業者単位に査定する |
- |
- |
- |
- |
|
③工事単位に査定する |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
④注文番号単位に査定する |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
⑤伝票単位に査定する |
○ |
○ |
○ |
○ |
★査定方法を、①仕入額を支払する②業者単位に査定するとしたときは、手形入力・協会費入力・相殺入力・その他控除入力は全て「しない」となります。
【Ⅱ 手形入力の有無による各種設定】
|
支払査定 |
支払確定 |
||
|
手形基準額 |
計算対象(郵送料) |
手形率100%で端数未満の扱い |
|
|
手形入力する |
明細単位 |
- |
- |
|
手形入力しない |
業者単位 |
○ |
○ |
参考例A : ① 仕入金額に対して満額査定する場合 ⇒ 仕入額を支払する
参考例B : ② 査定時に支払保留があるが、内訳は業者ごとに査定する場合 ⇒ 業者単位に査定する
参考例C : ③~⑤ 工事や注文番号単位、伝票単位に査定する場合
参考例A : ① 仕入金額に対して満額査定する場合 ⇒ 仕入額を支払する
・支払査定の入力不可
・内訳表示不可
・手形基準額:業者単位
・手形計算対象(郵送料)、手形率100%で端数未満の扱いの設定必須
仕入金額に対して、常に満額で支払をする場合は、査定方法を①「仕入額を支払する」に設定します。
【Ⅰ】査定方法が①「仕入額を支払する」の場合は、支払査定の内訳を入力できません。
【Ⅱ】支払査定内訳の登録ができないので、「手形入力」項目は「しない」という設定で固定されます。
これによって「手形基準額」項目が業者単位となり、「計算対象(郵送料)」項目、「手形率100%で端数未満の扱い」項目の設定が
必要となります。
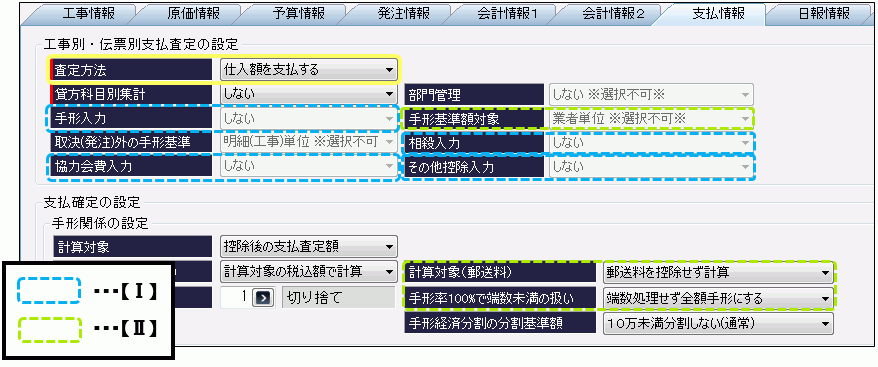
【Ⅲ】この設定の場合は、[支払査定(工事/部門別)]での査定入力ができなくなります。
ただし、査定金額の登録は必要となりますので、必ず[支払査定(工事/部門別)]から登録処理を行ってください。
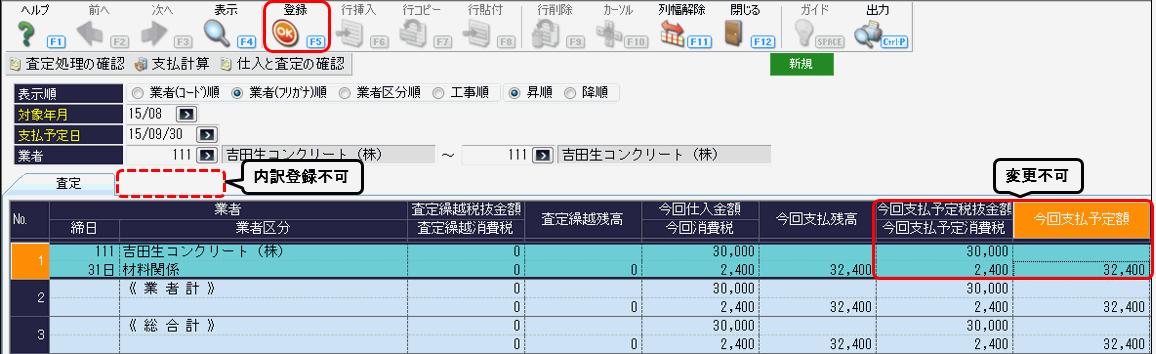
参考例B : ② 査定時に支払保留があるが、内訳は業者ごとに査定する場合 ⇒ 業者単位に査定する
・支払査定の入力可能
・内訳表示不可
・手形基準額:業者単位
・手形計算対象(郵送料):設定必須
・手形率100%で端数未満の扱い:設定必須
仕入金額に対して、支払保留もあるが、内訳の査定は業者ごとに行うという場合は、査定方法②「業者単位に査定する」を選択します。
【Ⅰ】査定方法が②「業者単位に査定する」の場合は、支払査定の内訳を入力できません。
【Ⅱ】支払査定内訳の登録ができないので、「手形入力」項目は「しない」という設定で固定されます。
これによって「手形基準額」項目が業者単位となり、「計算対象(郵送料)」項目「手形率100%で端数未満の扱い」項目の設定が
必要となります。
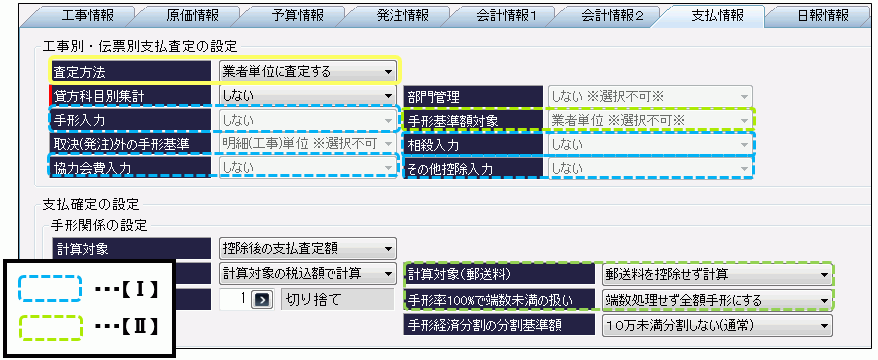
【Ⅲ】またこの設定の場合は、[支払査定(工事/部門別)]での査定入力が可能です。
今回支払残高に対する支払予定額を入力し、登録します。
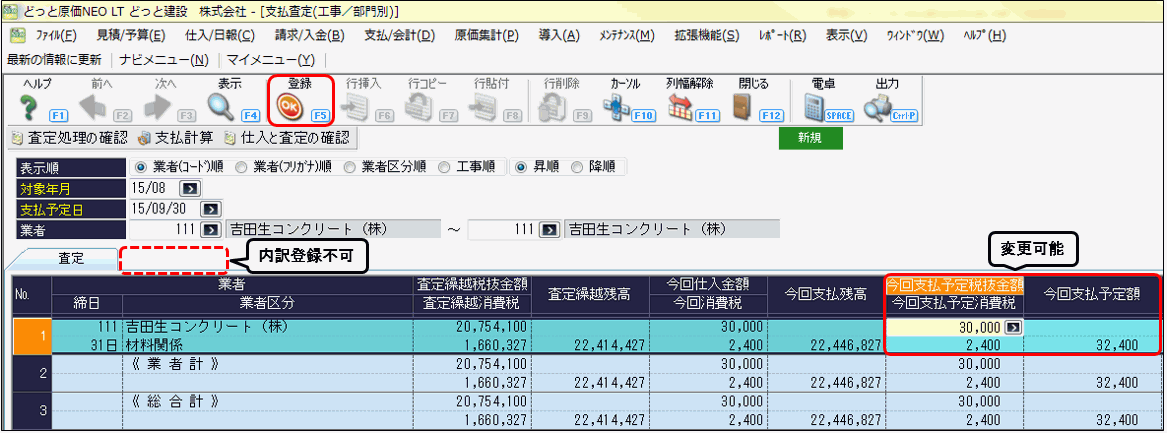
参考例C : ③~⑤工事や注文番号単位、伝票単位に査定する場合
・各単位ごとに支払査定
・査定内訳登録:各査定内訳の設定に依存
・手形基準額:手形入力設定に依存
・手形計算対象(郵送料):手形入力に依存
・手形率100%で端数未満の扱い:手形入力に依存
仕入金額に対して、工事単位・注文番号単位・伝票単位で査定する場合は③~⑤に設定します。
【Ⅰ】査定方法を、③「工事単位」④「注文番号単位」⑤「伝票番号単位」で査定する場合は、
各支払内訳(手形・協力会費・相殺・その他控除)を入力するかしないかの設定が行えます。
すべての内訳項目の入力を「しない」とした場合は、参考例A、Bのように[支払査定(工事/部門別)]『内訳』タブが表示されません。
【Ⅱ】「手形入力」項目を「しない」にした場合は、「手形計算対象(郵送料)」「手形率100%で端数未満の扱い」の設定が必要となります。
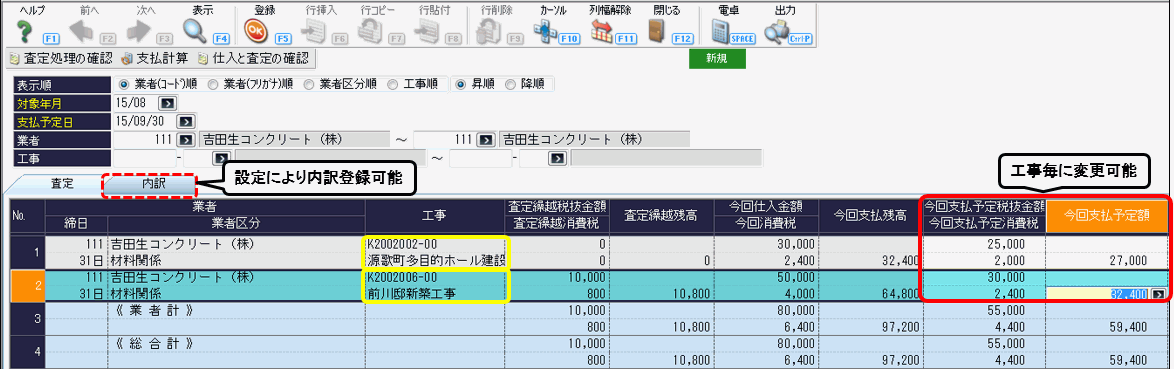
【Ⅲ】その他、これらの設定では、[支払査定(工事/部門別)]でそれぞれの単位で支払予定金額の査定が行えます。
例えば、査定方法を③「工事単位に査定する」とした場合は、各工事明細ごとに支払予定金額を入力します。