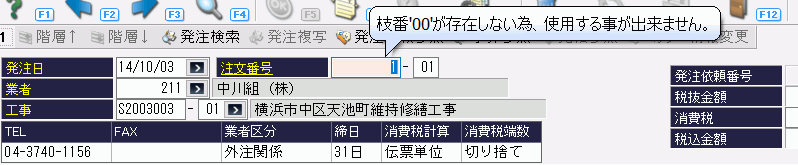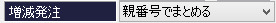増減発注について
|
増減分を枝番管理することにより、当初分に増減分を含めた発注残高の管理を行うことが可能です |
|
ナビメニュー:【発注処理】→[発注入力] 【見込管理】→[発注入力] (メニュー:【見積予算】→[発注入力]) |
増減発注概要
[初期設定]-『発注情報』の増減発注の設定を「する」にすることで、増減発注機能が使用できます。
増減発注機能を使用した場合、注文番号の枝番管理が行えるようになります。
枝番管理することで、当初発注分から変更があった場合に、増減分も含めて発注残高管理が行えるようになります。
 |
①当初発注分(親番号)と増減発注分(枝番号)の工事及び業者は同一の場合のみ登録可能です。 ②増減発注分(枝番号)が存在する場合、当初発注分(親番号)は削除することができません。 ③[発注依頼入力]では、増減発注の管理を行うことができません。 |
用語説明
本ソフトウェアでは、注文番号のXXXXXXXX-00(ハイフン以降が00)を親番号と呼び、XXXXXXXX-01~XXXXXXXX-99(ハイフン以降が01~99)を枝番号と呼びます。
例)
1-00 親番号
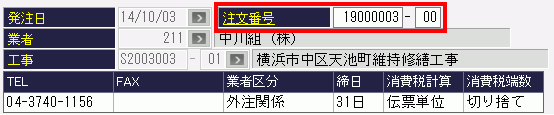
1-01~1-99 枝番号
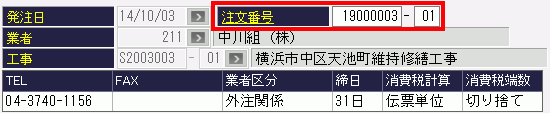
処理の流れ
①当初発注分(親番号)の登録を行います。
当初発注分(親番号)は、注文番号がXXXXXXXX-00(ハイフン以降が00)の番号で登録します。
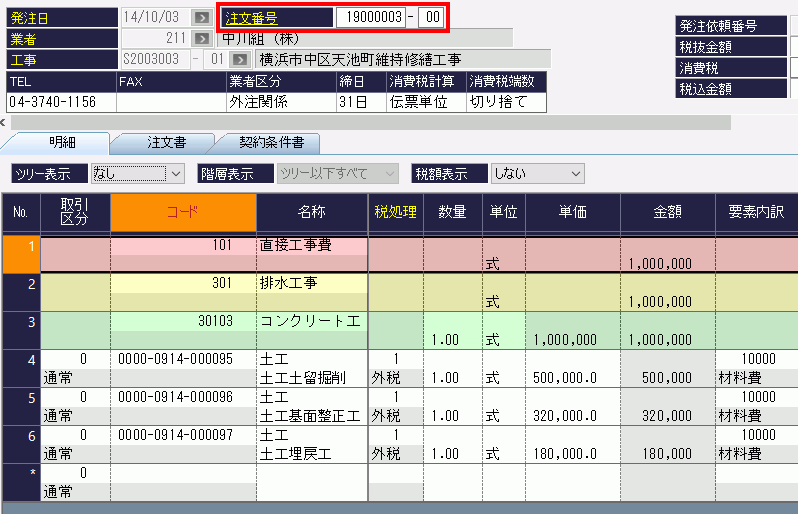
 |
親番号(XXXXXXXX-00)が無い状態で、枝番号(XXXXXXXX-01~XXXXXXXX-99)の登録はできません。
|
②増減発注分(子番号)の登録を行います。
増減発注分(枝番号)は注文番号が(ハイフン以降が01~99)で登録します。
当初発注分(親番号)を表示し、ハイフン以降の枝番号部分を手動で入力します。
なお、当初発注分(親番号)のデータを引き継いで増減分の入力を始めたい場合は、サブツールバーの「増減発注」をクリックします。
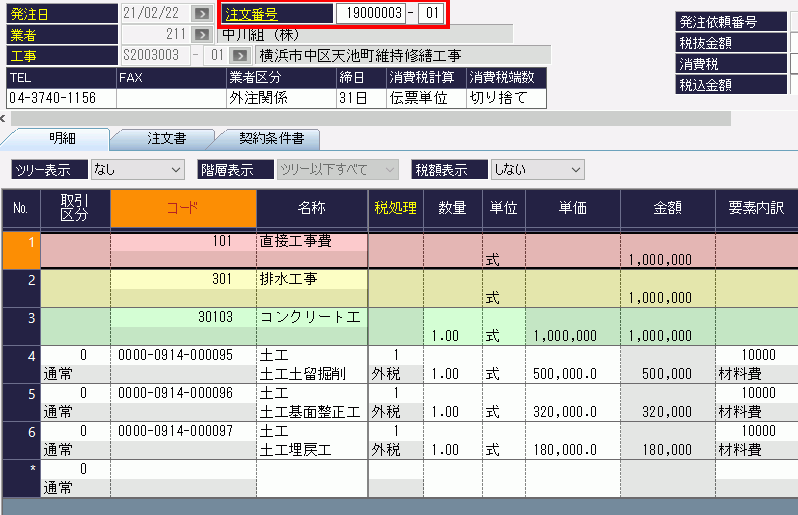
登録いただき、完了です。
 |
【増減発注を使用した場合に追加される条件】 増減発注を使用した場合、一部のメニューと帳票で以下図の増減発注設定が追加されます。
こちらの設定は、増減発注分を合算して抽出するか注文番号ごとに抽出するかの設定になります。 親番号でまとめる・・・XXXXXXXX-00の親番号にXXXXXXXX-01~XXXXXXXX-99の枝番号が合算されます。 個別の番号で表示する・・それぞれの注文番号ごとに集計されます。
※「親番号でまとめる」とした場合に、条件設定の発注日は親番号(XXXXXXXX-00)の発注日を検索します。 例) 注文番号:1-00 発注日:2016/10/01 発注金額:10,000円 注文番号:1-01 発注日:2016/11/01 発注金額: 5,000円
A、「親番号でまとめる」と設定し、発注日を2016/10/01で条件指定した場合、以下のように表示されます。 【注文番号:1-00 発注日:2016/10/01 発注金額:15,000円】
B、「親番号でまとめる」と設定し、発注日を2016/11/01で条件指定した場合、以下のように表示されます。 【該当データなし】
上記のように、枝番号(XXXXXXXX-01~XXXXXXXX-99)の発注日が条件指定した発注日に含まれる場合も、 親番号(XXXXXXXX-00)の発注日が該当していない場合は、表示されません。
↓↓条件設定に追加されるメニューと帳票は以下になります。↓↓ ≪メニュー≫
≪帳票≫ [注文書]、[注文書(内訳書)]、[発注業者査定表]、[発注一覧表]、[工事原価推移表]、[支払通知書]
|