会社設定
|
会社の情報を登録します |
|
(メニュー:【導入】→[設定]→[会社設定]) |
画面構成と入力項目
確認したいタブを選択してください。
基本情報セキュリティ消費税会社銀行採番情報端数情報印紙税社名編集自動連携バッチ設定
基本情報
基本操作画面
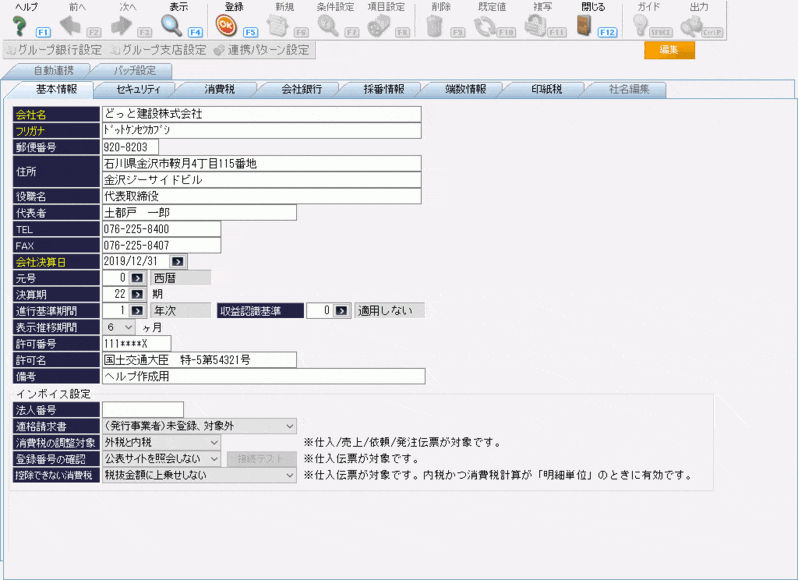
ツールボタン
|
ツールボタン |
説 明 |
|
ヘルプ (F1) |
ヘルプを表示します。 |
|
表示 (F4) |
最新情報を表示します。 |
|
登録 (F5) |
入力した情報を登録します。 |
|
閉じる (F12) |
画面を閉じます。 |
|
カレンダー (SPACE) |
カレンダーを表示します。 |
|
ガイド (SPACE) |
ガイドを表示します。 |
※グレーになっているボタンは使用できません。
入力・表示項目
|
項目 |
入力 |
属性・桁数 |
説 明 |
|
|
会社名 |
● |
全角15文字 |
会社名を入力します。 会社データ選択時に表示される会社名を変えたい場合は、 こちらから変更を行ってください。 |
|
|
フリガナ |
● |
半角12文字 |
フリガナを入力します。 会社名を入力したときのカナが自動入力されます。 変更も可能です。 |
|
|
郵便番号 |
○ |
半角8文字 |
郵便番号を入力します。 |
|
|
住所 |
○ |
全角25文字 |
住所を入力します。 郵便番号を入力すると住所が自動入力されます。 ただし、実在しない郵便番号を入力したり 既に住所が入力済みの場合は自動入力しません。 |
|
|
役職名 |
○ |
全角15文字 |
代表者の役職名を入力します。 |
|
|
代表者 |
○ |
全角15文字 |
代表者を入力します。 |
|
|
TEL |
○ |
半角18文字 |
電話番号を入力します。 |
|
|
FAX |
○ |
半角18文字 |
FAX番号を入力します。 |
|
|
会社決算日 |
● |
日付 |
会社決算日を指定します。 手入力または、ツールボタンの「カレンダー」から選択します。 入力した会社決算日までの1年間が会計期間となり、 ステータスバーに表示されます。 本ソフトウェア上で“今期”と表現された場合の“今期”とは、 こちらで設定した会計期間となります。 |
|
|
元号 ※1 |
○ |
数字1桁 |
本ソフトウェア上での暦表示を入力します。 「西暦」「和暦」から選択します。 |
|
|
決算期 |
○ |
数字2桁 |
決算期を入力します。 手入力または、ツールボタンの「電卓」から入力します。 |
|
|
進行基準期間 |
○ |
数字1桁 |
進行基準期間を入力します。 ここで設定した期間で進行基準の処理を行います。 「年次」「半期」「4半期」「月次」から選択します。 |
|
|
収益認識基準 ※3 |
○ |
数字1桁 |
収益認識に関する会計基準を適用するか選択します。 「適用しない」「適用する」から選択します。 |
|
|
表示推移期間 |
○ |
- |
本ソフトウェアから出力できる推移表関連の画面(※2)で 表示する推移期間を選択します。 「12」「6」から選択します。 |
|
|
許可番号 |
○ |
半角8桁 |
許可番号を入力します。 |
|
|
許可名 |
○ |
全角25文字 |
許可名を入力します。 |
|
|
備考 |
○ |
全角25文字 |
備考を入力します。 |
|
|
イン ボイス 設定 |
法人番号 |
○ |
数字13桁 |
法人番号(マイナンバー)を入力します。 |
|
適格請求書 |
○ |
- |
適格請求書発行事業者かを選択します。 「(発行事業者)未登録、対象外」「(発行事業者)登録済み」 から選択します。 |
|
|
消費税の調整対象 ※4 |
○ |
- |
消費税の調整対象を選択します。 「外税のみ」「外税と内税」から選択します。 |
|
|
登録番号の確認 ※5 |
○ |
- |
登録する際に、業者の登録番号を公表サイトに照会し、 仕入明細内の税額控除が適切かどうかを判定します。 「公表サイトを照会しない」「公表サイトを照会する」から 選択します。 |
|
|
接続テスト |
- |
- |
公表サイトに接続できるかを確認することができます。 |
|
|
控除できない消費税 ※6 |
○ |
- |
仕入明細を画面入力する際に、税額控除できない消費税を 税抜金額に上乗せするかを選択します。 「税抜金額に上乗せしない」「税抜金額に上乗せする」から 選択します。 |
|
(入力)●…必須入力項目 ○…入力項目
 |
【※1】日付入力方法に関して 西暦の場合は、数字4桁、和暦の場合は、元号+数字2桁になります。 元号部は数値(1:明治 2:大正 3:昭和 4:平成 5:新元号)で入力します。
【※2】推移表関連の画面に関して 下記メニューが推移表関連の画面に該当します。 対象メニュー:[仕入支払推移表]、[売上入金推移表]、[工事回収管理表]、[工事原価推移表]、
【※3】収益認識基準の適用に関して 「適用する」から「適用しない」への設定変更は、既に[工事登録]の「売上基準」が「原価回収基準」の データがある場合できませんのでご注意ください。
【※4】消費税の調整対象に関して
消費税端数処理が「切り捨て」の場合
なお、税率が複数ある場合、税率ごとに外税と内税の調整を行います。
調整額を反映後
もとに作成していますが、サービスの内容は国税庁によって保証されたものではありません。
適格請求書発行事業者公表サイトは以下URLからご参照ください。 https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
【※6】控除できない消費税に関して ・「税抜金額に上乗せしない」 内税、税込110円を入力した場合 → 「税抜100円、消費税10円」…従来通り ・「税抜金額に上乗せする」 内税、税込110円を入力した場合 → 「税抜102円、消費税8円」…消費税2円を税抜金額に上乗せ
具体的な計算方法は以下の通りになります。
※以下の場合に上乗せされます。 業者マスターの消費税計算「明細単位」、かつ、仕入明細の税処理「内税」 税額控除「控除80%」
下記メニューが該当します。([伝票データの整合機能]は対象外) 対象メニュー:[仕入伝票入力1]、[仕入伝票入力2]、[日報入力]、[勤怠入力(社員別)]、[機械稼働入力]、[汎用データ受入]
|
 |
工事進行基準と会社決算日について [会社設定]-『基本情報』の「会社決算日」を元に対象年月の1ヶ月を判断しています。 途中で会社決算日(3/31→3/20等)を変更すると工事進行基準を行った過去の内容の確認や 修正をすることができませんのでご注意ください。
|