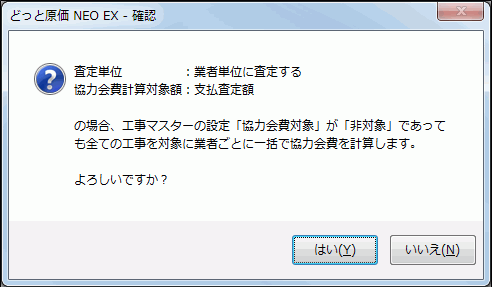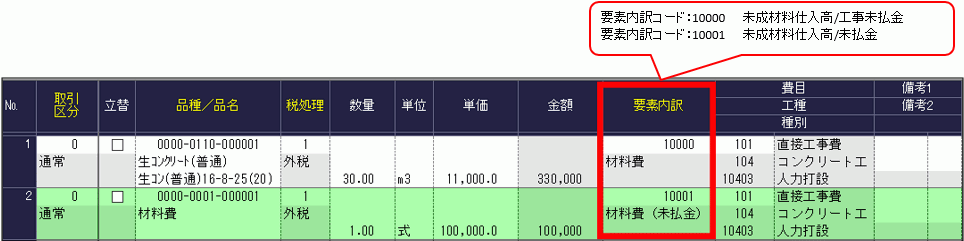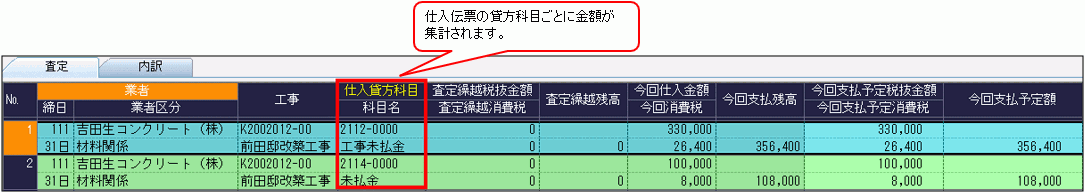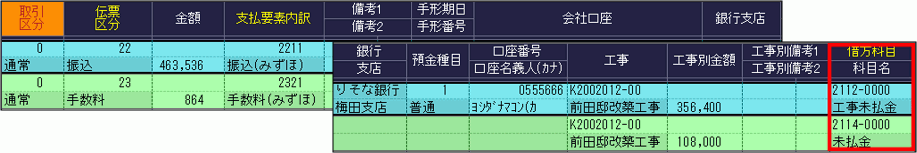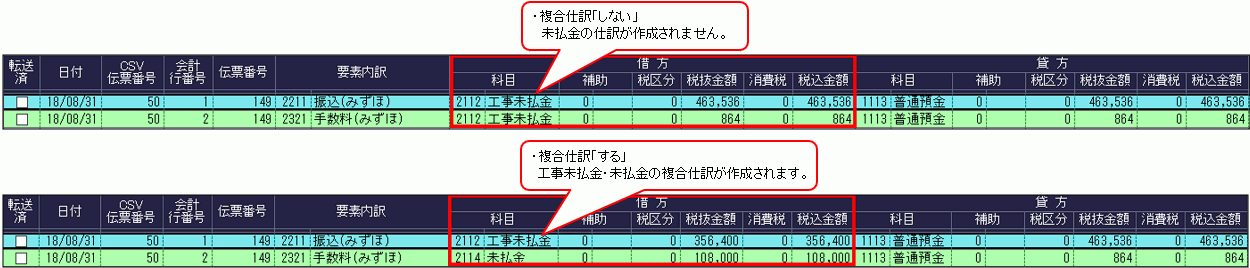初期設定
|
初期設定では、機能ごとに使用する項目の選択や入力方法、計算方法などの設定を行います。 |
|
ナビメニュー:【導入】→[初期設定] (メニュー:【導入】→[設定]→[初期設定]) |
画面構成と入力項目
確認したいタブを選択してください。
共通情報工事情報仕入情報予算情報発注情報会計情報1会計情報2支払情報日報情報勤怠情報機械情報請求情報見積情報承認情報労災保険顧客情報JV情報データ分析仮設資材
支払情報
 |
【途中での設定変更に注意が必要な項目】 途中で設定を変更する場合に注意が必要な項目に関しては、項目の頭に赤いラインが引かれております。
|
基本操作画面
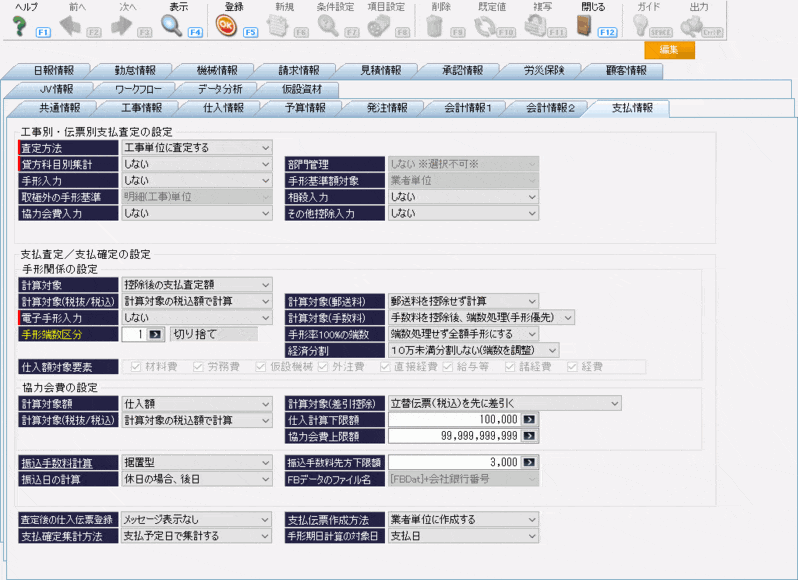
ツールボタン
|
ツールボタン |
説 明 |
|
ヘルプ (F1) |
ヘルプを表示します。 |
|
表示 (F4) |
最新情報を表示します。 |
|
登録 (F5) |
入力した情報を登録します。 |
|
閉じる (F12) |
画面を閉じます。 |
|
電卓 (SPACE) |
電卓を表示します。 |
|
ガイド (SPACE) |
ガイドを表示します。 |
※グレーになっているボタンは使用できません。
入力・表示項目
|
項目 |
入力 |
属性・桁数 |
説 明 |
||
|
工事別・ 伝票別 支払査定 の設定 |
査定方法 ※1、3 |
● |
- |
支払査定時の集計単位を設定します。 「仕入額を支払する」「業者単位に査定する」 「工事単位に査定する」「注文番号単位に査定する」 「伝票単位に査定する」から選択します。
支払査定方法の設定によってその他設定出来る箇所が 異なります。 詳しくは、◆補足◆ 支払査定方法についてをご参照ください。 |
|
|
貸方科目別 集計 ※1、2、4 |
● |
- |
貸方科目ごとに支払金額の集計を行うかを設定します。 「しない」「仕入の貸方科目別に集計」から選択します。 「仕入の貸方科目別に集計」を選択している場合、 支払複合伝票が作成できます。 |
||
|
部門管理 |
- |
- |
[支払査定(工事/部門別)]-『内訳』において、 部門ごとに小計行での支払金額の査定を行うかを設定します。 「しない」「する」から選択します。 ※現在は選択不可項目となっております。 |
||
|
手形入力 ※5 |
● |
- |
支払査定時に[支払査定(工事/部門別)]-『内訳』で 手形の入力を行うかを設定します。 「しない」「する」から選択します。 「査定方法」で「工事単位に査定する」 「注文番号単位に査定する」「伝票単位に査定する」を 選択している場合に表示されます。 |
||
|
手形基準額 対象 |
● |
- |
手形基準額の算出対象を設定します。 「業者単位」「明細単位」「合計のみ業者単位」から選択します。 「査定方法」で「工事単位に査定する」 「注文番号単位に査定する」「伝票単位に査定する」、 「手形入力」で「する」を選択している場合に表示されます。 詳しくは、◆補足◆ 手形基準についてをご参照ください。 |
||
|
取極外の 手形基準 |
● |
- |
発注を切っていない分に対する手形基準額の 算出対象を設定します。 「業者単位」「明細(工事)単位」から選択します。 「査定方法」で「注文番号単位に査定する」、 「手形入力」で「する」を選択している場合に表示されます。 詳しくは、◆補足◆ 手形基準についてをご参照ください。 |
||
|
相殺入力 ※3、5 |
● |
- |
支払査定時に[支払査定(工事/部門別)]-『内訳』で 相殺の入力を行うかを設定します。 「しない」「する」から選択します。 「査定方法」で「工事単位に査定する」 「注文番号単位に査定する」「伝票単位に査定する」を 選択している場合に表示されます。 |
||
|
協力会費 入力 ※5 |
● |
- |
支払査定時に[支払査定(工事/部門別)]-『内訳』で 協力会費の入力を行うかを設定します。 「しない」「する」から選択します。 「査定方法」で「工事単位に査定する」 「注文番号単位に査定する」「伝票単位に査定する」を 選択している場合に表示されます。 |
||
|
その他 控除入力 ※5 |
● |
- |
支払査定時に[支払査定(工事/部門別)]-『内訳』で その他控除の入力を行うかを設定します。 「しない」「する」から選択します。 「査定方法」で「工事単位に査定する」 「注文番号単位に査定する」「伝票単位に査定する」を 選択している場合に表示されます。 |
||
|
支払 査定/ 支払 確定 の 設定 |
手形 関係 の 設定 |
計算対象 |
● |
- |
手形計算をする際の計算対象を設定します。 「仕入額」「控除前の支払査定額」 「控除後の支払査定額」から選択します。 |
|
計算対象 (税抜/ 税込) |
● |
- |
手形計算をする際の計算対象を税抜金額か税込金額の どちらにするかを設定します。 「計算対象の税抜額で計算」「計算対象の税込額で計算」 から選択します。 |
||
|
計算対象 (郵送料) |
● |
- |
手形計算時、計算対象金額に郵送料を含むかを設定します。 「郵送料を控除後計算」「郵送料を控除せず計算」から 選択します。 |
||
|
電子手形 入力 ※1 |
● |
- |
電子債権の達人連動を行うかどうかを設定します。 「しない」「する」から選択します。 ご参照ください。 |
||
|
計算対象 (手数料) ※15 |
● |
- |
電子手形計算時、計算順を設定します。 「手数料を控除後、端数処理(手形優先)」 「端数処理後、手数料を控除(手形優先)」から選択します。 「手形入力」で「しない」を選択している場合に選択できます。 |
||
|
手形端数 区分 |
○ |
数字1桁 |
手形計算時に発生した端数処理方法を設定します。 「切り捨て」「四捨五入」「切り上げ」から選択します。 |
||
|
手形率 100%の 端数 |
● |
- |
手形率100%の場合の手形端数未満の金額について 設定します。 「端数処理ぜす全額手形にする」「端数を値引きにする」 「端数を現金または振込にする」から選択します。 「手形入力」で「しない」を選択している場合に選択できます。 |
||
|
経済分割 ※6 |
● |
- |
手形を経済分割する際の分割基準額を設定します。 「10万未満分割しない(端数は無視)」「10万未満分割する」 「300万以上は10万未満を分割する」 「10万未満分割しない(端数を調整)」から選択します。 |
||
|
仕入額 対象要素 |
● |
- |
手形計算をする際の仕入額対象要素を設定します。 「計算対象」で「仕入額」を選択している場合に選択できます。 |
||
|
協力 会費 の 設定 |
計算 対象額 ※7 |
● |
- |
協会費計算をする際の計算対象を設定します。 「仕入額」「支払査定額」から選択します。 |
|
|
計算対象 (差引控除) ※8 |
● |
- |
協力会費計算時、計算対象金額に控除金額を 含むかどうかを設定します。 「立替伝票(税込)は計算後差引く」 「立替伝票(税込)を先に差引く」 「立替伝票(税込)を先に差引く(下限の判断も同様)」 から選択します。 |
||
|
計算対象 (税抜/ 税込) |
● |
- |
協会費計算をする際の計算対象を税抜金額か 税込金額のどちらにするかを設定します。 「計算対象の税抜額で計算」「計算対象の税込額で計算」 から選択します。 |
||
|
仕入計算 下限額 ※9 |
○ |
数字11桁 |
協会費を計算しない場合の仕入下限額を設定します。 ここで設定した金額より仕入金額が小さい場合、 協力会費の計算を行いません。 手入力または、ツールボタンの「電卓」から入力します。 |
||
|
協力会費 上限額 ※10 |
○ |
数字11桁 |
協力会費の上限額を設定します。 手入力または、ツールボタンの「電卓」から入力します。 |
||
|
振込手数料計算 ※11 |
● |
- |
振込手数料の計算方法を設定します。 「据置型」「未満手数料加算型」「以上手数料加算型」から 選択します。 |
||
|
振込手数料先方 下限額 |
○ |
数字11桁 |
振込手数料を先方負担としない仕入下限額を設定します。 設定した金額より振込金額が小さい場合、[業者登録]の 振込手数料負担が先方負担でも当方の負担となります。 |
||
|
振込日の計算 ※12 |
● |
- |
振込日が休日の場合について設定します。 「業者登録通り」「休日の場合、前日」「休日の場合、後日」 から選択します。 |
||
|
FBデータの ファイル名 |
- |
- |
FBデータ作成時のファイル名の形式を設定します。 「前回記憶値(1行分)」「FBDat+会社銀行番号」から 選択します。 ※現在は選択不可項目となっており、 「FBDat+会社銀行番号」となります。 |
||
|
査定後の仕入伝票登録 |
● |
- |
支払査定処理を行った後で仕入登録を行った場合に、 再度支払査定を行うよう警告するメッセージを表示するかを 設定します。 「メッセージ表示なし」「警告メッセージ表示」から選択します。 |
||
|
支払伝票作成方法 ※4 |
● |
- |
[支払伝票転送]において支払伝票を作成する 方法を設定します。 「業者単位に作成する」「明細(工事)単位に作成する」から 選択します。 |
||
|
支払確定集計方法 ※13 |
● |
- |
[支払確定]において集計方法を設定します。 「仕入月+支払予定日で集計する」「支払予定日で集計する」 から選択します。 |
||
|
手形期日計算の対象日 ※14 |
● |
- |
手形期日を計算する際の対象日を設定します。 「支払日」「支払予定日」から選択します。 |
||
(入力)●…必須入力項目 ○…入力項目
 |
【※3】 「査定方法」「相殺入力」に関して 「査定方法」が「注文番号単位に査定する」かつ「相殺入力」が「する」の場合、 『仕入情報』の仕入伝票入力の表示の「立替入力の表示」は、「仕入伝票入力1のみ」しか選択できません。
【※4】 「支払伝票作成方法」に関して 設定によって、同一業者別工事の仕入から作成する支払伝票の金額集計方法が以下のように変わります。 ・「業者単位に作成する」 工事は考慮せず業者ごとに金額を集計して支払伝票を作成します。 ・「明細(工事)単位に作成する」 支払伝票作成時、工事ごとに金額を集計した工事別の支払伝票も作成されます。 「貸方科目別集計」の設定で、仕入の貸方科目別に集計に設定した場合、必ず支払伝票の作成方法は 「明細(工事)単位に作成する」に固定されるのでご注意ください。
【※5】 支払査定内訳に関して 「手形入力」、「相殺入力」、「協会費入力」、「その他控除入力」のいずれかの項目で「する」を選択している場合、 [支払査定(工事/部門別)]-『内訳』が表示されます。「しない」を選択している場合は、 支払金額の内訳を[支払査定(工事/部門別)]-『内訳』ではなく[支払確定]で行うことになりますので、 [支払査定(工事/部門別)]には『内訳』が表示されません。 詳しくは、◆補足◆ 支払査定方法についてをご参照ください。
【※7】 協会費設定の計算対象額 ・「仕入額」 [仕入伝票入力1]、[仕入伝票入力2]、[日報入力]などで登録されている金額を元に協会費を計算します。 ・「支払査定額」 [支払査定(工事/部門別)]で査定した今回支払予定額を元に協会費を計算します。
工事別・伝票別支払査定の設定の「査定方法」が「業者単位に査定する」かつ 協会費設定の「計算対象額」が「支払査定額」の場合、[工事登録]の「協会費」の設定が無効になります。 「協会費」が「非対象」の工事があっても全ての工事を対象とし、協会費を計算しますのでご注意ください。
【※8】 「計算対象(差引控除)」に関して ・「立替伝票(税込)は計算後差引く」 計算対象額をもとに協力会費を算出します。 ・「立替伝票(税込)を先に差引く」 計算対象額から立替金額(税込)を差し引いた金額をもとに協力会費を算出します。 (仕入計算下限額は計算対象額で判断) ・「立替伝票(税込)を先に差引く(下限の判断も同様)」 計算対象額から立替金額(税込)を差し引いた金額をもとに協力会費を算出します。 (仕入計算下限額は差し引いた金額で判断)
【※9】 仕入計算下限額を設定しない場合 仕入計算下限額を設定せず、仕入の金額がいくらであっても協会費を計算したい場合は、仕入計算下限額を 「-99,999,999,999」と入力してください。
【※10】 協会費上限額を設定しない場合 協会費の上限額を設定しない場合は、協会費上限額を「99,999,999,999」と入力してください。
(詳しくは、◆補足◆ 振込手数料計算についてをご参照ください) ・「据置型」 差し引き前の振込金額で計算する方法で、差し引いた金額より実際の手数料が少なくなる場合があります。 ・「未満手数料加算型」 据置型の振込金額範囲に10,000円未満、30,000円未満の手数料を足したものを 新たな手数料テーブルとして計算する方法で、差し引いた金額より実際の手数料が少なくなる場合があります。 ・「以上手数料加算型」 据置型の振込金額範囲に10,000円以上、30,000円以上の手数料を足したものを 新たな手数料テーブルとして計算する方法で、差し引いた金額より実際の手数料が多くなる場合があります。
【※12】 「振込日の計算」に関して ・「業者登録通り」 振込日が休日の場合も[業者登録]-『支払情報』に登録した支払日で処理します。 ・「休日の場合、前日」 [業者登録]-『支払情報』に登録した支払日が休日の場合、その前日を振込日として処理します。 ・「休日の場合、後日」 [業者登録]-『支払情報』に登録した支払日が休日の場合、その後の日を振込日として処理します。
また、「休日の場合、前日」と「休日の場合、後日」の設定を行う場合、 事前に[カレンダー]で祝日設定を行う必要があります。
【※13】 「支払確定集計方法」に関して ・「仕入月+支払予定日で集計する」 仕入月(対象年月)と支払予定日が同じ場合に、[支払確定]で支払計算をまとめて行うことが可能です。 ・「支払予定日で集計する」 仕入月(対象年月)が異なっていても、支払予定日が同じであれば、 [支払確定]で支払計算をまとめて行うことが可能です。対象年月の指定は出来ません。
[支払査定(工事/部門別)]は、どちらも仕入月と支払予定日ごとに行います。
例)業者A 現金振込種別:「振込」、手形率:50%、端数額:100,000円 〈仕入〉
〈支払査定〉
〈支払確定〉 ・「支払確定集計方法」:「仕入月+支払予定日で集計する」の場合 対象年月(仕入月)・支払予定日ごとに、金額を集計・計算します。 その為、1と2で2回計算が必要になります。
・「支払確定集計方法」:「支払予定日で集計する」の場合 支払予定日のみで、金額を集計・計算します。 その為、1と2は支払予定日が同日なので、1回で計算できます。
|
 |
【※6】 手形経済分割の分割基準額 ①10万未満分割しない(端数は無視) ②10万未満分割する ③300万以上は10万未満を分割する ④10万未満分割しない(端数を調整) 以上①~④の設定をした場合、以下表のように印紙税が計算されます。
(例)
【※14】 「手形期日計算の対象日」に関して 手形期日を計算する際の対象日が以下のように変わります。 「振込日の計算」によって支払日が変わる場合に、影響します。 ・「支払日」 支払日から手形期日を算出します。 ・「支払予定日」 支払予定日から手形期日を算出します。
例)業者A 手形サイト:4ヶ月後末、仕入伝票:支払予定日「3/31(日)」 〈振込日の計算:休日の場合、後日〉 ・「手形期日計算の対象日」:「支払日」の場合 支払日「4/1(月)」から算出します。手形期日は「8/31」になります。 ・「手形期日計算の対象日」:「支払予定日」の場合 支払予定日「3/31(日)」から算出します。手形期日は「7/31」になります。
【※15】 「計算対象(郵送料)」「計算対象(手数料)」に関して 「計算対象(郵送料)」は手形、「計算対象(手数料)」は電子手形の計算に関わる設定です。
*1 郵送料の控除は現金または振込から優先的に行います。 *2 項目に「(手形優先)」の記載有無で、手数料の控除先が変わります。 電子手数料負担が「当方負担」の場合、手数料の控除は行いません。 ・「(手形優先)」あり 手数料の控除は電子手形から行います。 ・なし 手数料の控除は現金または振込から優先的に行います。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
【手形基準とは?】 手形基準とは、手形で支払う場合の基準値のことを意味します。 [業者登録]-『支払情報』の「手形基準額」で業者別に基準額を設定することができます。
|
 |
【※1】 「査定方法」「貸方科目別集計」「電子手形入力」の切り替えに関して 運用の途中で「査定方法」「貸方科目別集計」「電子手形入力」の設定を切り替えると、 切り替える以前に発生した仕入がすべて繰越金額と計上されてくることになります。 そのため、一度運用を開始した後は、途中での変更は行わないようご注意ください。
また、「査定方法」において「仕入額を支払する」を選択している場合は、[支払査定(工事/部門別)]での 査定入力ができなくなります。 ただし、査定金額の登録は必要となりますので、必ず[支払査定(工事/部門別)]から登録処理を行ってください。
【※2】 「貸方科目別集計」の使用方法に関して 貸方科目別集計を「仕入の貸方科目別に集計」と設定している場合、仕入伝票で選択されている 要素内訳の貸方科目ごとに支払金額が集計され、支払伝票が作成されます。
仕訳データ転送(支払)を使用される場合は、仕訳データ転送の条件設定で 「複合仕訳」を「する」に設定していただく必要があります。 ※「複合仕訳」が「しない」になっている場合、業者登録の支払情報に依存して仕訳が作成されるため、 仕入時の科目と相殺されない場合があります。
<イメージ図> ・仕入伝票
・支払査定 仕入伝票で登録されている要素内訳の貸方科目ごとに金額が集計されます。
・支払伝票
・仕訳データ転送
|